この度はオペラバフの宮廷楽士長と奥様女中のセット公演にご来場いただきまして誠にありがとうございました。

モーツァルト以前の古典ブッファの名作を上演させていただきましたがご堪能いただけましたでしょうか?
2作品とも一時間にも満たない小さな作品ですがとても難しくて作品の良さをお伝えできたかどうかちょっと自信がありません。
歌手やオーケストラの方達に頑張っていただいたので手前共といたしましては精一杯やらせていただいた達成感はございます。
何が難しかったかと申しますと正直申し上げてどうやって良いのか分からないのです。
暗中模索と申しますかイタリアで連綿と続いてきたコメディデラルテの伝統の型はどのようなものなのか、どうやればそれに近いものになるのか、答えはありませんでした。

これは現代にあってはないものねだりなのかもしれません。
YOU TUBE等で奥様女中の一流の歌手たちの映像を観ても上手いとは思うものの伝統はあまり感じられませんでした。もしかしたらイタリアでも断絶しているのかもしれません。
それと比較いたしますと我が国の歌舞伎は連綿と家の芸が子孫に伝えられております。江戸時代のものがすべて相伝で伝わっているわけではないでしょうが人気演目や得意演目はほぼ伝わっているのではないでしょうか。
チマローザの宮廷楽士長はモノオペラで出演者はバリトン一人です。演技は歌手の自由裁量に任されています。もしこれが歌舞伎の演目だとしましたら團十郎型や菊五郎型が出来たでしょうし成田屋、播磨屋あたりが十八番や秀山十種とかに加えていたかもしれません。
またぺルコレージの奥様女中は歌舞伎であればセルピーナは女形ですが親子共演や兄弟共演でヴェスポーネはその家の気のきいた弟子が演じたのかもしれません。
こうした想像は楽しいのですが果たしてオペラの世界で宮廷楽士長であればブルスカンティーニ型やコレナ型があるものなのでしょうか?
思うにそのようなものはその歌手一代限りで後進の歌手たちはそれを教わりこそすれ自分のオリジナルを追求したのではないのでしょうか。
オペラ歌手は世襲ではありません。

そういたしますと正解や手本はないわけでとにかく芝居上おかしいことが無いように楽譜に忠実に再現するしかない訳であります。
奥様女中の稽古中にこんなことがありました。
後半ヴェスポーネが軍人に化けて登場する場面で間が空くというのでモーツァルトのドンジョバンニの騎士長の登場のテーマをチェンバロで演奏してはどうかという提案があり実際にやってみましたが見事にそれまでの感じが台無しになりました。
当たり前のことですがモーツァルトとぺルコレージは全く別物なのですね。
これで音楽にも型があることを学びました。

良く勘違いで受けを狙って他の音楽を入れたり笑いを取るために余計な演技をしたりする風潮がありますがこれはナンセンスで禁じ手です。
逆説的にシリアスに演じればこそ笑いが取れるのです。
今の日本のオペラ公演の現状は安易に流れる傾向にあります。いつも同じような演目をやってお茶を濁したりいい加減にモーツァルトなどをやって初心者向きとしたりなど嘆かわしい限りです。
真摯に古典に立ち返り取り組む団体、歌手が出てくればという願いでオペラバフはこの演目を上演いたしました。
次回はトマのハムレットです。
またの御贔屓よろしくお願いします。
オペラバフ 制作代表
宇田川慎介





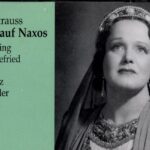
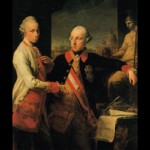



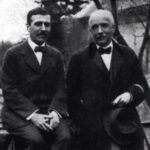

この記事へのコメントはありません。