これまで2回にわたり、チマローザの大まかな生涯に触れて参りましたが、ここからは私たちが良く知る作品や作曲家との関わりについてお話しいたします。
この時代のナポリは、まさに百花繚乱でして、あまたの音楽家が集まってきています。中でもチマローザと因縁が深いのが、ジョヴァンニ・パイジエッロ(Giovanni Paisiello, 1740 – 1816)です。ターラント(イタリア半島の踵に位置する)に生まれたパイジエッロは、やはり美声により注目を浴び、ナポリに送られてフランチェスコ・ドゥランテ(1684 – 1755)に師事します。ドゥランテはイタリア古典歌曲の『愛に満ちた処女よ Vergin, tutto amor』や『踊れ、やさしい娘よDanza, fanciulla gentile』などの作曲で有名ですね。対してパイジエッロはオペラ『水車小屋の娘 La molinara』(1790年作曲)の中のアリア『もはや私の心には感じない(うつろの心)Nel cor più non mi sento』が有名です。
このパイジエッロもチマローザと同じく、ロシアのエカチェリーナ2世に呼ばれて、彼の地で『セヴィリアの理髪師 Il bariere di Sviglia』を書き上げます。これは後年、ロッシーニによって同じ台本に作曲され、現在では忘れ去られておりますが、当時大ヒットとなった作品で、ヨーロッパを席巻したのでした。ちなみにパイジエッロはペルゴレージの『奥様女中 La Serva Padrona』と同じ台本に作曲して、逆に名声を横取りした経緯がありました。
それは兎も角、このパイジエッロがチマローザとライバル関係になります(パイジエッロはペルゴレージに対しても批評的だったようです)。彼との不和が、チマローザの晩年を暗いものにする一因になったようです。
さて前回、チマローザの晩年は、フランス革命の余波により、運命が激変するお話をしました。
革命思想に魅了されて愛国的讃歌を作曲しますが、これが為に王政復古後に「革命派」と目されて投獄されてしまうわけです。
この時の王様がフェルディナンド4世で、女王がマリア・カロリーナ・ダズブルゴ(Maria Carolina d’Asburgo、1752年8月13日 – 1814年9月8日)です。フェルディナンド4世は、政治に興味はなく、刈りやスポーツに熱中するタイプだったようで、実際の政治は妻であった女王のマリア・カロリーナがおこなっていたそうです。
マリア・カロリーナがどんな方だったか…と言うと、これが面白いのです。この方の両親は神聖ローマ帝国皇帝フランツ1世と女帝マリア・テレジアで、彼女は10番目の子供です。その下(15番目の子供)に生まれたのが、マリー=アントワネット=ジョゼフ=ジャンヌ・ド・アプスブール=ロレーヌ、すなわち後にルイ16世に嫁ぎ、『ベルサイユのばら』の主人公の一人となった人です!(笑)
元々、マリア・カロリーナは、ナポリに嫁ぐ予定は無かったのです。彼女の夫になるはずの人は、なんとフランス王ルイ16世!?そう、マリー=アントワネットの旦那さんです。彼女の姉のマリア・ヨーゼファがナポリ王に嫁ぐはずが、1767年、結婚直前に急死。そのため、翌年にマリア・カロリーナがナポリに嫁ぐことになります。この突然の結婚に、同じ部屋で過ごしており、マリア・カロリーナに懐いていたマリー=アントワネットは、痛く悲しんだそうです。
これが、とんでもない伏線になります!
フランス革命が起きた時、マリア・カロリーナは革命側…市民たちに同情を寄せていたらしいです。元々彼女は、ナポリ国内でフリーメイソン活動に手を貸していたりしたそうです。また中には女性が加入できる団体もあったそうです。どうも反革命的な女性というより、啓蒙君主的に見えますね。他にもスペインの政治的干渉を退けたり、士官学校を作って軍隊を再編したりと、政治的に大変有能だったことがわかります。
ところが妹のマリー=アントワネットが、夫と共に断頭台の梅雨と消えた!と聞いて震え上がります。マリア・カロリーナとルイ16世は婚約までは至っていなかったようですが、神聖ローマ帝国の皇女として、どの王国に嫁いでもおかしくなかったわけで、自分自身がルイ16世と共に死刑になっていた可能性もあったわけです。そして亡くなったのは、自分に懐いていたマリー=アントワネットです!フェルディナンド4世とマリア・カロリーナは、反革命に舵を切ります。
さあ、ここから皆さん良くご存知のオペラの話に入って参ります。『トスカ』です!
このマリア・カロリーナに革命派の取り締まりを任されていたのが、スカルピア男爵です。革命派と目されていたアンチェロッティに脱獄され、これを捕らえられないと自分の首が危ない!と必死になります(サルドゥの原作では、スカルピア男爵がマリア・カロリーナ女王に脅されるシーンがあります)。だから拷問でも何でもやります。
そして第2幕ファルネーゼ宮殿にて、スカルピア男爵が窓の外から流れてくるトスカの歌声に耳を傾けるシーンがありますが、これは原作のこのシーンを元にしていると思われます。
トスカはマリア・カロリーナの前で歌うことになっていましたが、すぐにでもカヴァラドッシの元に行きたくて、演奏を拒否します。スカルピア男爵に「演奏後には、すぐ出発できるように馬車を用意するから…」と宥められて、トスカは渋々、受け入れます。チマローザの前に現れたトスカは「これじゃ音が高い!」と文句を言い、慌てたチマローザがオーケストラに音を下げて演奏するように言います…。
なんで革命派として逮捕され、牢獄に入れられたチマローザが、マリア・カロリーナの前で演奏ができるのだ?と思われた方もいらっしゃるでしょう。実は史実でチマローザは革命派が敗れた後、『フェルディナンド4世の帰還のためのカンタータ Cantata pel ritorno di Sua Maestà Ferdinando IV』を作曲することで、新当局に恩を売り、逮捕を免れようとしていたのです。結局、狙い通りにはいかず、チマローザは牢獄に入ることになりますが。
ちなみにチマローザのライバル、パイジエッロは1816年に両シチリア王国の国歌(inno nazionale del Regno delle Due Sicilie)として採用された『フェルディナンド王、万歳(Viva Ferdinando il re)』(1787年、王より委嘱)を作曲しています。
チマローザもパイジエッロも、フェルディナンド4世(Ferdinando IV – マリア・カロリーナの夫)を賛美する曲を書きますが、一人は投獄され、故郷のナポリから追放。もう一方は、その曲が両シチリア王国の国歌として採用される栄誉を得る…なんとも言えない気持ちになりますね。
でも、プッチーニの『トスカ』の2幕の舞台裏では、チマローザ作曲・指揮でトスカが歌っている…と想像するのも一興ではありませか?
岡野 守 プロフィール
バス・バリトン。イタリア・モデナ在住。
早瀬一洋、Arrigo Pola、Carmela Stara、Luciano Berengo、Giuliana Panza に師事。
ペルゴレージ作曲『奥様女中』(Uberto)、モーツァルト作曲『ドン・ジョヴァンニ』(Leporello)、『コシ・ファン・トゥッテ』(Don Alfonso)、ロッシーニ作曲『セヴィリアの理髪師』(Don Bartolo)、ドニゼッティ作曲『愛の妙薬』(Dulcamara)、ヴェルディ作曲『運命の力』(Fra Melitone)、ビゼー作曲『カルメン』(Dancairo)、プッチーニ作曲『トスカ』(Il Sagrestano)、『ジャンニ・スキッキ』(Gianni Schicchi)、『トゥーランドット』(Ping)等を歌っている。藤原歌劇団団員。
オペラを中心に声楽家として活動していたが、師匠たちから「お前は、私の知らないことばかり知っている!」「Musicologo(音楽学研究家)もやれ!」と言われ、良い気になって、雑学的音楽コラムを書き始める。



公演チケットのお申し込みはこちら -『宮廷楽士長』『奥様女中』2本上演



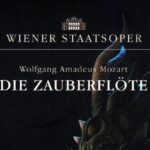



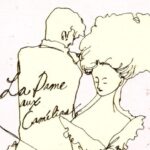




この記事へのコメントはありません。