素人、アマチュアの方がオペラに関わることは合唱が近道なのですが他にも関わる方法があるかどうかを考察してみます。
オペラは言うまでもなく総合芸術です。
様々な仕事の分野があり細分化されています。

上演に際しての縁の下の力持ちである裏方の仕事を経験するのも得難い経験が出来るでしょう。
ただ専門分野はプロが動かしているケースが多いのでその下働きに入ることになります。
覚悟しなくてはいけないのはオペラの裏は結構殺気だっていてピリピリしています。
それぞれプロの仕事ですから妥協はありません。現場ではスタッフ弁当を食べる暇もないほど忙しいです。
怒鳴られることもあるでしょう。お客さん扱いはしてくれません。
ただ真剣で真面目に取り組んでいれば貴重な戦力、仲間として扱われ「次もお願い」とか「うちの会社に来ないか」などと言われます。

この業界も慢性的に人手不足なのです。
本当に舞台が好きであればともかくちょっと年輩のお父さんにはしんどいかもしれません。
今後舞台に関わりたく仕事にしたいと考えている若い方にはいいでしょう。
簡単に各部門ごとに素人で関われる仕事をまとめてみましょう。
衣裳
読んで字のごとく出演者の衣裳を用意して整える部門です。
裁縫がありますので必然的に女性が多いですが和服の着付けなど意外と力仕事もありますので男性の方もいらっしゃいます。
ボタン付けや裾上げ、アイロンがけが手伝える仕事でしょう。
他には舞台袖での早着替えの手伝いくらいでしょうか。
ヘアメイク
ここは高等技術が必要な部門です。
美容師の資格をお持ちであれば重宝されるでしょうがメイクさんは個々に自分の趣味や流儀がありそれに即して手伝うことが重要です。
残念ながら素人にはあまり関われる仕事はありません。
自分でメイクをしないといけない合唱団の方のメイクを手伝うことくらいでしょうか。
舞台監督助手
小屋に入りましたら全責任は舞台監督に帰属します。
彼の手足となる仕事です。
仕込み段階の舞台の設営、終演後のばらし,後片づけが主な仕事となります。
開演前、上演中の使い走りもあります。
出演者に予定を口頭で伝えるタイムキーパー、問題のある観客の処理など結構大変です。
事故が起こらないように細心の注意を払うのが舞台監督ですから常に彼の先回りをして気を回すと重宝がられます。逆に気が回らないとぼこぼこにされます。

制作
要するに雑用です。
本番と稽古の会場確保、ソリストの出演交渉、関係者への連絡、チラシ、プログラム作成と広報宣伝活動、チケット販売、果ては小屋入り後のスタッフ弁当の手配まであります。
上演時は表で観客の世話です。もぎり、案内、出演者への差し入れ、伝言の預かり業務、苦情処理など仕事は数限りなくあります。
とにかくオペラを計画立案して稽古から上演そして終演までスムーズに事が運ぶようにあらゆる仕事をこなすのが使命です。
案外この部門は営業、総務、経理経験があるお父さんが結構役に立ちます。
また器用な方は小道具、大道具の制作に関われるかもしれません。
演出助手
演出家の手伝いです。
ある意味これが一番きついかもしれません。
立ち稽古はすべて出席する義務があります。もしあなたが将来演出家の道に進もうと考えていらっしゃるのならばまたとないチャンスです。
演出家の意図を正しく理解して出演者に伝えたり質問を受けたりします。
立ち稽古は誰よりも早く来て場ミリテープを床に貼ったり、小道具等の準備をします。(場ミリとは出演者が想像しやすい様に本番の舞台の寸法通りにビニールテープを貼ることです)
演出家が出席している時は隣に座り演出家が囁くダメ出しを紙に書き出しそれを出演者に伝えます。
要領がつかめないソリスト、合唱団にアクションのきっかけを教えます。
演出家が不在の時は稽古自体を仕切らなくてはなりません。
このように立ち稽古中は気を抜く暇はありません。
演出家の考えを的確に理解して人に伝える仕事は予想外に大変です。
まず演出家の構想を理解するには作品のみならずあらゆることを勉強しなければなりません。
時間とやる気があれば一念発起して挑戦してみるのもいいでしょう。

音楽スタッフ・照明
副指揮者やピアニスト(コレペティ)は音楽的素養と技術が必要なので素人は関われません。
但しあなたがアマチュアオケマンでインスペクター経験者であればオーケストラの下働きとして重宝がられるでしょう。
照明はプロの方の場合手下を連れてくるケースが多いので関わることは不可能でしょう。
そして小屋の中ではどの部門の方達も暗黙の了解で黒のTシャツを着ています。
いかがですか?
なかなかどれも大変です。
制作の一部を合唱団の方が担当している団体もございますが裏方の方はあまり出番が無いようですね。
ここはとりあえず合唱にしておきましょう。
(続く)










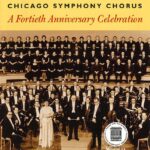

この記事へのコメントはありません。